こんにちは✿
みなさんは、ニュースを見るときどういう観点で見ていますか?
私は、ニュースを見るときは、見たことをそのまま鵜呑みにしないように意識しています。
今日はそんな私の情報の受け取り方をHSPの目線で紹介します(*^^*)
というわけで、今回は、
- HSP目線で情報を上手く受け取るコツ
- メディアリテラシーを向上させる方法
についてブログを書いていこうと思います!
HSPとは?
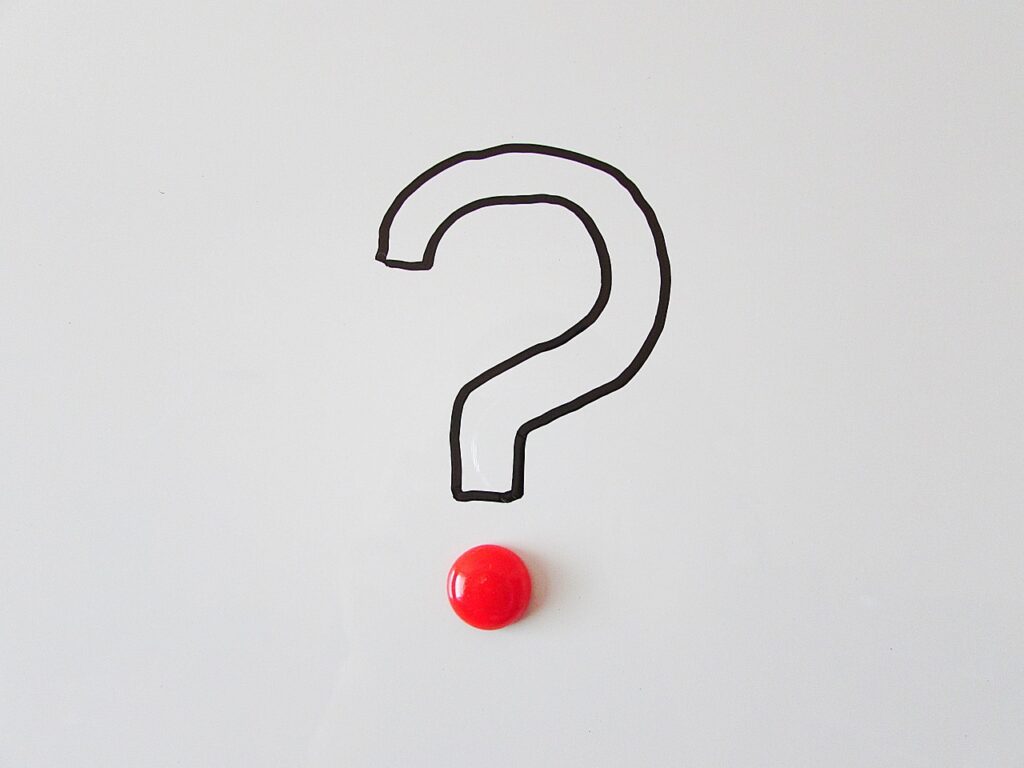
HSPは、Highly Sensitive Person(ハイリー・センシティブ・パーソン)の略称です。なんだか病名のように聞こえるかもしれませんが、これは遺伝子的に生まれ持った気質のことで、アメリカの心理学者であるエレイン・N・アーロン博士が提唱した心理学的概念です。
生まれつき「非常に繊細な人」「敏感な人」「感受性が強い人」などという意味です。
全人口の約5人に1人はこのHSPに当てはまっているそうです。
HSPについてまとめた記事もあるので、興味がある方はぜひ。
HSP関連の本はこちらから。
HSPの観点から見た最近のメディアの視聴傾向

共感疲労によりニュースを避ける
共感力がとても高いHSPは共感疲労を感じやすい傾向にあります。
共感疲労とは、他人が経験した出来事やトラウマに共感することで、自分の経験ではなくても疲労を感じてしまうストレス反応です。
最近ではインターネットの普及で、ますます共感疲労を感じやすくなっていると思います。

個人的に戦争や災害の映像が苦手です…。
HSPの暗いニュースとの付き合い方はこちら。
イギリスの調査などによると共感疲労のせいで、ニュースを避ける傾向にあるそうで、自分の目に入ったニュースのみが真実だと誤認するようになってきているそうです。

さらにそのニュースの信憑性を別のメディアで検証しなくなってきてもいるようだよ。
映像メディアを作業BGMとしてラジオ感覚で聞く
HSPは刺激に弱いので、その影響を最小限に抑えるため、「音声のみ」でニュースを知るのがおすすめです。
映像と音声の2つで見るより、映像メディアをラジオ感覚で聞く方が刺激も少なく、情報を受け入れやすくなるかと思います。

居心地がいい場所になったり、精神的にも安心するよね
悪意がない発信者も一所懸命になる
悪意がなく、何気ないメディアでもその情報が真実ではない場合があります。
悪意がない発信者であっても、世間の注意を引くために、その情報が真実ではない場合であっても熱意を持って発信してしまうからです。
なので、情報の信頼性を確認し、クリティカルシンキングの観点で(批判的な視点を持ちながら)情報を受け取ることが大切です。
フェイクニュースや誘導的報道の危険性
フェイクニュースや誘導的な報道は、危険な影響を与える可能性があります。
その情報が真実でないことを知ることができないため、混乱や不安を引き起こすことがあります。また、HSPは感受性が高いため、このような報道が心理的に悪影響を及ぼす可能性があります。
HSPの特性を考慮して真実を見極める対策

音声や映像は重要な情報源ですが、感受性が高いHSPにとっては悪い影響となる場合があるため、自分の感情や精神的な状態を考慮しながら、「どのような情報」の「どの程度」を受け取るかを選択することが必要です。
メディアリテラシーを向上させる
まずは、メディアリテラシーを向上させましょう。
メディアリテラシーとは、様々なメディアの情報を正しく理解し、主体的に読み解く能力を指します。
メディアリテラシー向上の課題としては、まずは情報の信憑性を見極める能力を養うことです。
HSPは感情的な刺激に強く反応するため、情報が本当かどうかを冷静に判断するのが難しい場合があります。そのため、信頼できる情報源を見極めることや、複数の視点から情報を確認するメディアリテラシーが重要です。
この課題を克服するためには、次のような方法があります。
●情報の出所や背景を確認:
まず、情報の出所や背景を確認することが大切です。公正で客観的な情報を提供する独立系メディアや信頼性の高いメディアからの情報を重視することが大切です。
●情報の受け取り方を工夫する:
情報の受け取り方においても、冷静かつ客観的な視点を持つためのトレーニングが必要です。自分の感情に流されず、事実に基づいた判断を行うことが、HSPにとってメディアリテラシーの向上につながります。
「自分好みのメディア + 独立系メディア」で情報の信頼性が高くなる
HSPにとって独立系メディアは、情報の信頼性を確保する上で重要です。
独立系メディアは商業的な圧力や政治的な影響を受けにくく、客観的で信頼性の高い情報です。

独立系メディアは、番組制作時にスポンサーが絡んでいないから、スポンサーに配慮した偏見が少ないよ。
この点で、独立系メディアは他の商業メディアよりも信頼できる情報だと思います。独立系メディアが提供する情報は、HSPが情報を受け入れる際の安心感に繋がります。
そのため、HSPは日常的な情報収集において、自分の趣味趣向に合ったメディアだけでなく、独立系メディアをある一定の真実の指標として見るのが好ましいと思います。
インフルエンサーなどの意見はどう受け取る?
その情報に特化した専門家などの意見は参考になると思います。
しかし、エンタメ系のインフルエンサーに関しては、専門性がない可能性が高いので、その人の

この人の言っていることは正しくないかもしれないけど、、この人のファンだから参考程度に聞こう。
という姿勢ならば問題ないと思います。
真実を見極めるデモンストレーション

自分のメディアリテラシーがどの程度か確かめる問題(クイズ)を考えてみました。
日頃のニュースで私が注意している視点から問題を作ったので、一度試してみてください。
メディアリテラシーを確認するクイズ
【問題】
ある会社では「みかん、リンゴ、ブドウ」3種類のジュースを合計して「1か月約100万本」生産・出荷している。
その中でも、みかんジュースの人気が高く、内訳は、みかんジュースが60万本、リンゴジュースが30万本、ブドウジュースが10万本となっている。
これは公開情報のため世間の大半の人は知っている(この問題文自体に嘘はありません)。
以上を前提に、次のようなニュースが映像メディアで流れたとします。
問題と会見を合わせた場合、チェックすべきポイントは何でしょうか?
クイズのどの部分をチェックするべきか
【チェックポイント①】
●知識不足を補う
まずは、ジュースメーカーの公開情報を知っているかどうかです。知らない場合は、公開されている情報を調べればいいだけです。

「知らない=メディアリテラシーが低い」じゃないよ。
業界誌や国のHPを参照すればいいと思います。
公開情報には偏見が少ないため、独立系メディアで調べる必要はないと思います。(全ての情報をチェックするとキリがありません)
【チェックポイント②】
●数字の確認
大きい数字は人にインパクトを与え、また、注意を引き付けることができます。

このクイズにおいては「100万本の回収は大変な作業だね。回収費用も廃棄費用もすごい多いね」と誤認する人が多いかも。
ただし、読み解くと、
製造ラインの不備があったのは「7月1日~9日の9日間(1/3か月)」。よって、この間に生産・出荷した製品は約30本であり、100万本ではありません。
数字により印象操作されやすいので注意が必要です。
【チェックポイント③】
●スポンサー企業への配慮はないか
ジュースメーカーの主力製品はみかんジュースにもかかわらず、アナウンサーは「ぶどうジュースを始めとして・・・(略)」と報道しています。
公開情報のとおりに「みかんジュースを始めとして」と報道していないことには注意が必要です。
メディア側の一方的な忖度なのか、それともジュースメーカー側が、

主力製品のイメージを下げたくないので、名前を出すのは控えてください。
とメディア側に指示したのかは不明です。
また、画面を切り替えたときのジュース製品のパッケージのフリップ映像の中で説明があればいいのですが、この映像メディアをラジオ感覚で聞く人には、仮に映像内で説明があったとしても確認することができません。
「ジュースメーカーに不具合があった」という情報だけを浅く知るだけならいいですが、「このジュースメーカーのジュースには不良品がある」という深い情報までを受け取りたい人は、独立系メディアでの真実の確認が不可欠だと思います。

ジュースを他の固有名詞に置き換えると日常生活でも使えるようになるよ。
このような観点を意識するのもメディアリテラシー向上に役立ちます。
まとめ:自分の特性を考慮しつつニュースを見る目を養おう
というわけで、「情報の受け取り方のコツ」についてまとめてみました。
- 物事を主体的に読み解く力(メディアリテラシー)を向上させる
- ニュースなどの真実を見抜く力を養う
HSPの私目線での考え方でしたが、いかがでしたでしょうか。
HSPは物事を深く考えてしまう特性があり、ニュースなども深く考える傾向があります。その深く考える特性を活かして、情報の真意を捉えられるようになると、情報に踊らされたりせずに、少し生きやすくなるのかなと思います(^^)
この記事が少しでも参考になれれば嬉しいです。
ここまでブログを読んでくれてありがとうございます。
それでは✿
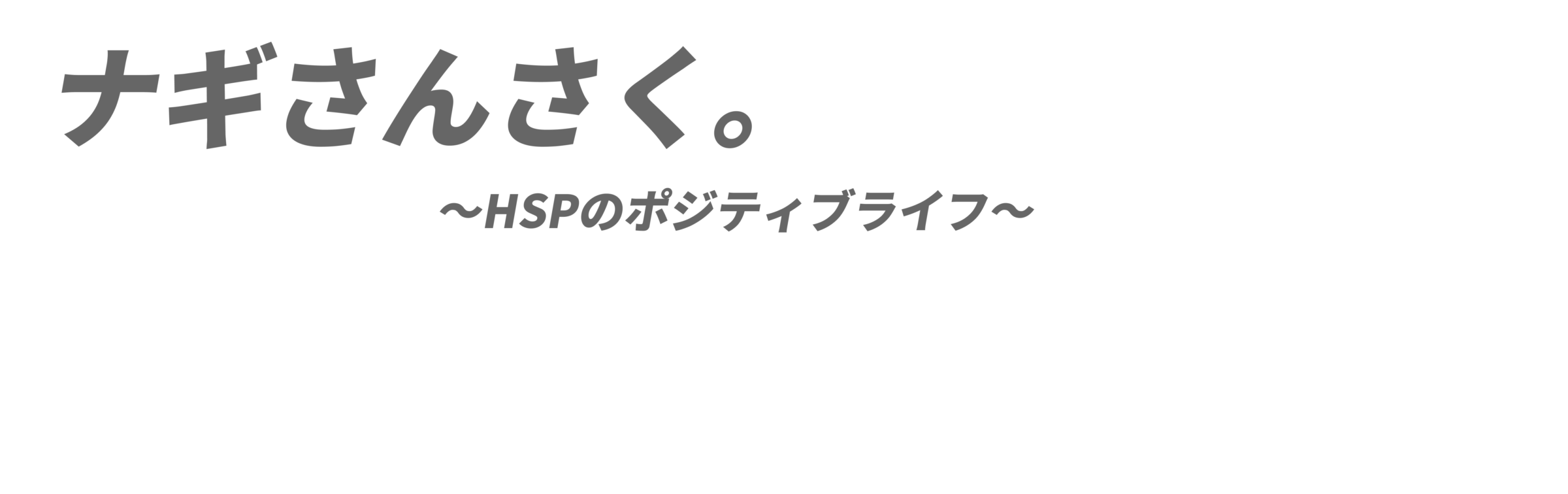
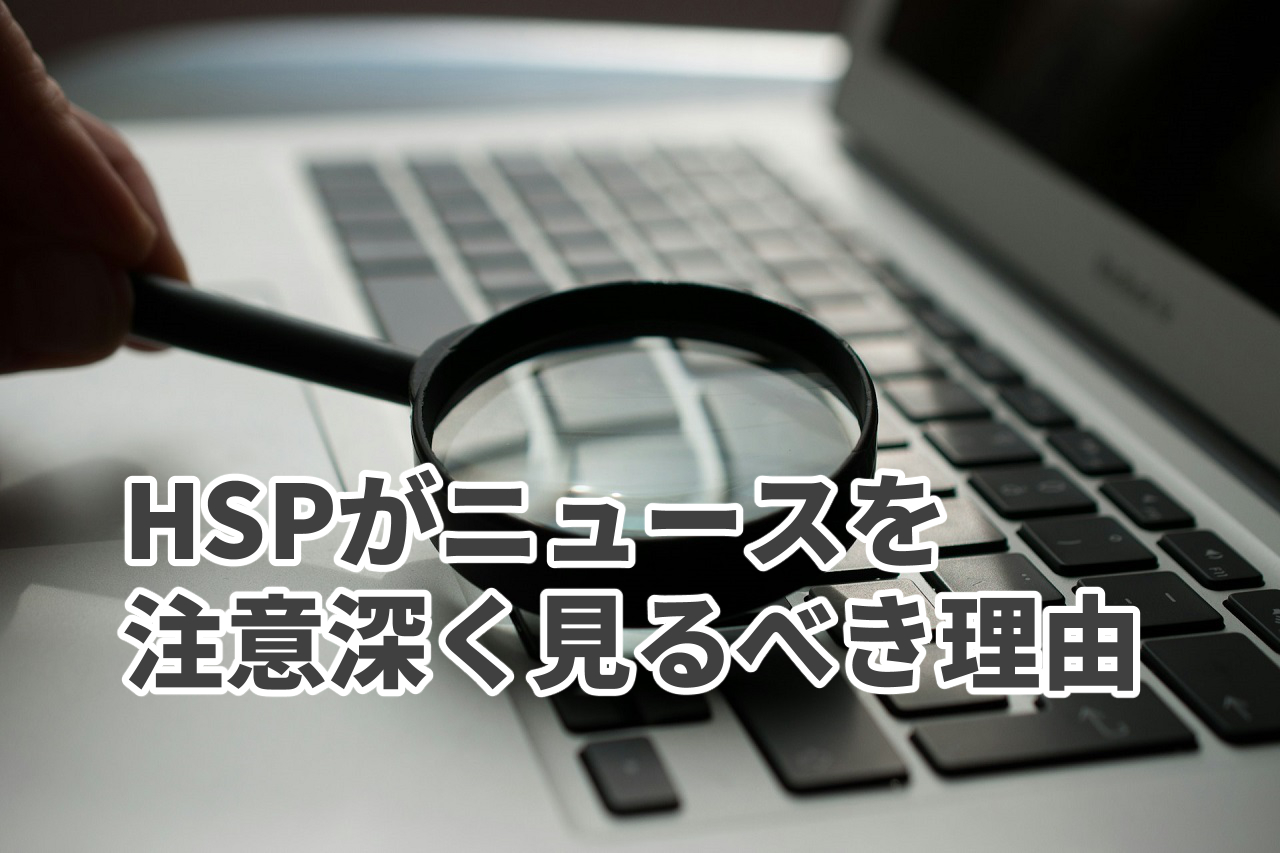



コメント