こんにちは✿
みなさんは「自立」と聞くと何を思い浮かべますか?
- 親元から離れて生活する
- 一人暮らしをする
- 自分の力のみで何とかする能力を養う
など色々あるかと思います。
今日は、

自立するために、引っ越しの詳しい手順を知りたい。
という人向けにブログ記事を書こうと思います。
「HSPが自立するための事前準備」と題して3部作にまとめてきましたが、今回は最後のPart③です!
Part①はこちら。
Part②はこちら。
というわけで、今回のブログテーマは「HSPが自立するための事前準備③ ~一人暮らし編~」です(*^^*)
HSPとは?
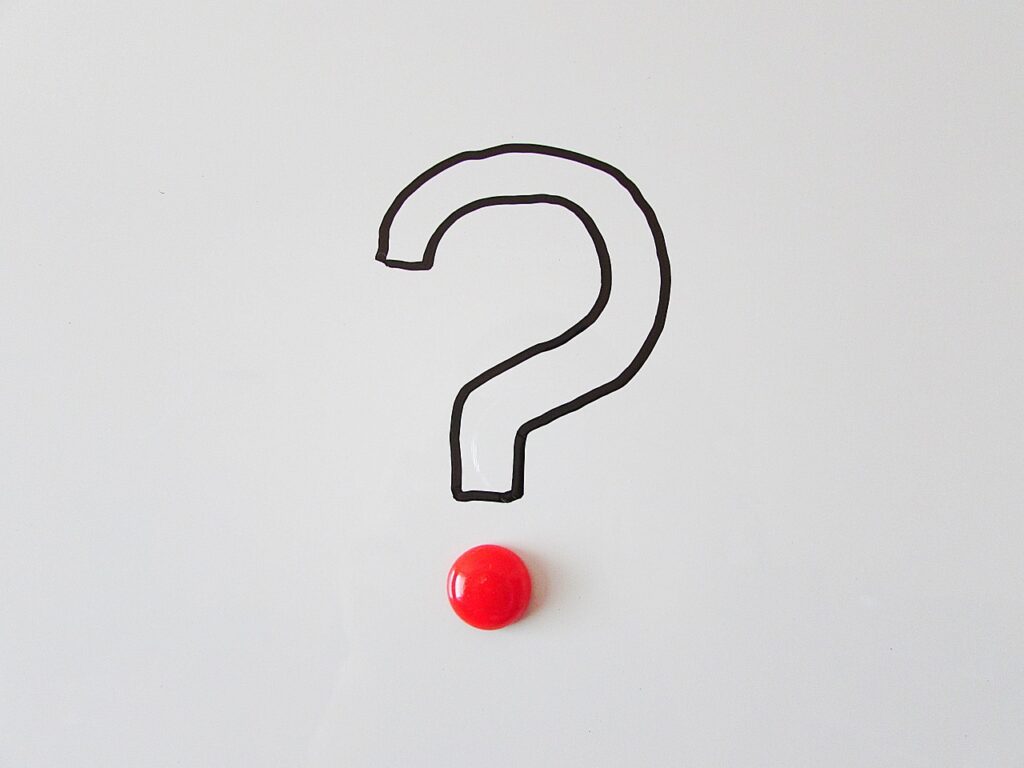
HSPは、Highly Sensitive Person(ハイリー・センシティブ・パーソン)の略称です。なんだか病名のように聞こえるかもしれませんが、これは遺伝子的に生まれ持った気質のことで、アメリカの心理学者であるエレイン・N・アーロン博士が提唱した心理学的概念です。
生まれつき「非常に繊細な人」「敏感な人」「感受性が強い人」などという意味です。
全人口の約5人に1人はこのHSPに当てはまっているそうです。
HSPについてまとめた記事もあるので、興味がある方はぜひ。
HSP関連の本はこちらから。
HSPにとって自立しようとする気持ちが大切な理由

きれいごとだけでは生活していけない現実がある
まず、HSPが自立するためには、理想論だけでは生活は難しいことを認識することが大切です。
自分の感受性や特性を理解しつつも、社会や生活のルールにも対応できるようにしなければなりません。
例えば、家計の管理や日常のルーティーンを整えることは、感受性が強い人にとっても重要です。一歩ずつ現実的な計画を立て、それを実行することが不可欠です。
HSPが抱えるもうひとつの問題は、あまり現実を知らない、ということだ。勘に頼ろうとして、人に尋ねることを嫌うからだ。しかし、現実の世界に生きている他の人から具体的な情報を集めることは、とくに内向的で直感的な人にとっては、大切な「個性化のプロセス」のひとつである。
ささいなことにもすぐに「動揺」してしまうあなたへ。 P.194
繊細だからといって何もしないわけにはいかない
HSPは感受性が高いため、ストレスや不安を感じやすいことがあります。しかし、それが理由で何も行動しないというわけにはいきません。
自分の感情や心の状態を理解しつつも、自分自身で行動し、問題を解決していくことが必要です。自己管理やストレス管理の技術を学ぶことで、自分の感受性を生かしつつ、生活の質を向上させることが可能です。
頼れる人がいなくなるかもしれない
自立する過程で、親や信頼できる人から離れざるを得ないこともあります。
特にHSPの場合、安心感や支えが欠かせないと感じることが多いかもしれませんが、いつかは自分自身で立ち上がって進んでいくときがきます。

できる限り自分の力で生きれるように努力したいよね。
新たな環境で自分を頼りにしながら、自信を持って、まわりに適応していくことが重要です。
HSPが自立するメリット

1人の時間が増える
HSPには、1人の時間が必要と言われています。
HSPは人や環境からの刺激に弱いので、その刺激から避けられる環境、つまり1人の時間がないとストレスが溜まります。自立し、一人暮らしをすると定期的に1人の時間が取れやすくなります。

1人だとまわりからの刺激はほぼ0だもんね。
1人時間だと自分が好きな環境で好きなことができるので、かなりのストレス解消になります。
生活力が上がる
一人暮らしをすると、生活に関することを全て1人でしなくてはなりません。そうなると、必然的に生活力が上がります。

HSPに限ったことではないけど、社会人として生きていくためには必須の能力だね。
生活力を上げるには、
- お金の管理ができる
- 家事全般はできる
- 自己管理ができる
などということが必要で、一人暮らしをしたらこういったスキルがアップするのが見込めます。
精神的に強くなれる
一人暮らしをすると、誰かに頼る機会が少なくなり、自分で考え、行動する力が養えます。他人の考えに引っ張られがちなHSPにとって「自分軸」を鍛えるトレーニングになりえます。
自分軸で考え、行動できると生活で起きるトラブルも自分の力で解決できるようになります。

自分1人でトラブルが解決できると責任感も養われるね。
また、今まで一緒にいた家族の大切さにも気付くこともできます。家族から離れて一人暮らしの苦労を経験すると実家の有難みを感じ、家族に感謝の気持ちが芽生えます。
感謝できる気持ちは心が強い証拠なので、人として成長できるのも期待できます。
はじめて一人暮らしする時の効率的な引っ越しの手順

※項目をクリックするとページ内のリンク(次の段落)に飛びます。もっと詳しく知りたい場合は、リンク先も読んでみてください。
- step 1
生活リズムや勤務場所を考慮して、焦らずに納得できる住まいを見つけましょう。
- step 2
契約時に審査があります。審査には一定の条件があるので、契約完了まで安心できませんが、会社員の場合はほとんど問題なく通過すると思います。
※毎月支払う家賃総額が手取り給料の3割程度なら審査合格すると思います。 - step 3
状況にもよりますが、引っ越し業者を手配した日から逆算して引っ越し日を決めてもいいかもしれません。
- step 4
入学や異動のタイミング3・9月は引っ越しの繁忙期のため、希望日時に手配できなかったり割り増し料金となる可能性があります。特に時間指定がしづらい場合がありますので、ご注意ください。
- step 5
引っ越し日に間に合うように、直近で使用しないものを中心に、少しづつ荷造りしておきましょう。
- step 6
引っ越し業者との契約時に新居に運ぶ予定ではなかった大型家電や大型家具などの大きな物以外なら、引っ越し当日(搬出日)までに購入して段ボールに詰めておけば、引っ越し業者に運んでもらえます。
大型家電を購入する場合は、購入時に新居に配送するように手続きしてください。ただし、配送日は新居に入居する日以降になるように日時を調整してください。 - step 7
- step 8
新居と旧居との距離が離れていると行ったり来たりが面倒になるので、旧居に住んでいる間に「転出届」を出し、役所から「転出証明書」を受け取っておきましょう。
※「転出届の届け出」は新居からの郵送にも対応していますが、郵送の方が面倒だと個人的には思います。役所に行く時間がない人以外は、できるだけ役所窓口で手続きすることをおすすめします。 - step 9
物件を仲介した業者に初期費用を払います。
不動産契約時に物件仲介業者は「重要事項説明」をしなければならないと法律で定められています。1時間くらいかかりますが、法律なので省略はできません。せっかくなので、しっかりと聞いて、わからない点は質問しておきましょう(「初期費用の支払い」と「重要事項説明」のスケジュールは物件仲介業者と調整しましょう)。
その後、新居の鍵を受け取ります。どのくらい前に鍵を受け取れるか確認しておきましょう。 - step 10
引っ越し業者が旧居に来ます(おそらく2名)。業者が部屋から荷物を出してトラックに積み込むのを、ただひたすら待つだけです。一人暮らし向けの荷物なので30分くらいで搬出は終わると思います。トラックへの積み込み作業が完了すると、作業漏れがないか確認します。その後に、書類にサインしたら搬出完了です。
基本的にはここで引っ越し費用の支払が行われます。現金を準備しておきましょう(キャッシュレス払いに対応している引っ越し業者もあります。支払い方法について、気になる方は事前に確認しておきましょう)
※謝礼金(チップ)を払うかどうかはご自分で決めてください。払う場合でも、おそらく2名なので「1,000円(500円 × 2)」くらいでいいと思います。 - step 11
当日に荷物の搬入まで終わらせる場合は、引っ越し業者に「●時〇分くらいに新居に到着します」と伝えるだけでOKです。自家用車や公共交通機関などで移動しましょう。
県外など遠方への引っ越しのため搬入と搬出が別々の場合は、この日の引っ越し作業は終わりです。引っ越し契約時に書類に書いた日時に間に合うように新居に移動しましょう(翌々日13:00頃に新居で待っているなど)。 - step 12
引っ越し業者が新居に来ます(搬出時とは違う人かもしれません。搬出時と同じで、おそらく2名です)。業者がトラックから荷物を出して部屋に運ぶのを、ただひたすら待つだけです。一人暮らし向けの荷物なので30分くらいで搬入は終わると思います。部屋に運ぶ作業が完了すると、作業漏れがないか確認します。その後、書類にサインしたら搬入完了です。
最後に、業者の方にアンケートはがきなどの書類を渡されて、お礼の挨拶をすると引っ越しは終わりです。
※搬出作業時の2名と違う場合に、謝礼金(チップ)を払うかどうかはご自分で決めてください。搬出時同様におそらく2名なので「1,000円(500円 × 2)」くらいでいいと思います。 - step 13お隣さんへのあいさつ
少なくとも自分の部屋の両隣りのお宅には挨拶した方がいいと思います。大袈裟な挨拶ではなく、「隣に引っ越してきた●●(名前)です。よろしくお願いします。引っ越しの片付けで、半月くらいうるさくしてしまうかもしれません。ご迷惑にならないように作業します」などでいいと思います。また、安価な土産(数百円のもの)を添えると気持ちが伝わりやすいと思います。生活消耗品(ティッシュや洗剤など)や菓子など個人差で好き嫌いが分かれる物以外なら何でもいいと思います。
- step 14
引っ越し後、下記の要件にしたがって2週間以内に役所に届出を提出しましょう。
① 旧居と新居が別の市区町村の場合
→「転入届」と「転出証明書」
② 旧居と同じ市区町村の場合
→「転居届」のみ - step 15
新居もしくは勤務先の最寄りの銀行(銀行の支店窓口)で住所変更しましょう。
- step 16
税金・社会保険・年末調整などに関わります。勤務先の総務担当に確認しましょう。
- step 17
Amazonなどの会員サービスの住所変更も忘れずにしておきましょう。
- step 18完了
ミッションコンプリート!これで全て終わりです。
おつかれさまでした。新天地での生活に慣れるように頑張りましょう。
私が思う効率的な手順は以上のようになります。あくまでも、はじめての一人暮らしを想定しています。
「一人暮らし中のアパート(旧居) → 一人暮らし中のアパート(新居)」の場合は、少しだけ応用すればほぼ同じような流れになると思います。
次の段落で補足説明をします。
引っ越しでやることを詳しく解説

家探しする
- 物件探し(※注1)
→ 焦らず納得がいく物件にしましょう。 - 申し込み、審査、契約
- 初期費用の準備
→ 敷金・礼金、火災保険料、仲介手数料
町内会費(※注2)、前払い家賃(※注3)
※注1)物件敷地内の駐車場でも別契約になる場合があります。物件仲介業者から聞いて確認しておきましょう。
※注2)町内会費の支払タイミングや支払方法は住まいによって異なるため、物件仲介業者から聞いて確認しておきましょう。
※注3)前払い家賃とは:「入居日~当月末分の家賃」と「翌月分の家賃」のことです。
引っ越し業者を手配する
- 複数業者で見積り費用を比較する
→ 「あなたの会社は●●円なんですね。昨日見積もりしてもらった業者さんは○○円だったんですが、もう少し安くなりませんか?」など、交渉の余地はいくらでもあります。時間に余裕があるなら、2社以上に見積りしてもらうことをおすすめします。 - 荷造りする
→ 引っ越し業者との契約が終わると、ほとんどの場合、段ボールとガムテープを無料でもらえます。あらかじめ個数とサイズを確認しておき、契約時に業者に伝えましょう。余っても追加費用は発生しないため、ある程度の余裕をもった個数にしておきましょう。 - 引っ越し日時を決める
→ 搬出(住んでいる部屋から荷物を出す)と搬入(引っ越し先に荷物を運ぶ)が別日でも問題ありません。
インフラの手続きをする
- 電気の開通手続き
- ガスの開栓手続き
- 水道の使用開始手続き
- インターネット回線の開通手続き(プロバイダ契約)
役所に届出を出す
- 役所に住所変更の届出を出す
| 新しい住所 | 届け出る役所 | 必要な届出 | 期限 | 代理 | 郵送 |
|---|---|---|---|---|---|
| 別の 市区町村 | 旧居の役所 | ・転出届を出す (・印鑑証明証の抹消手続き) | 引っ越し前後 2週間以内 | 可 | 可 |
| 転出証明書を受け取る (新居の役所に出すときに使用する) | ― | ― | ― | ||
| 新居の役所 | ・転入届を出す (・印鑑証明証の登録手続き) | 引っ越し後 2週間以内 | 可 | 不可 | |
| 転出証明書を出す (旧居の役所で受け取ったもの) | ― | ― | ― | ||
| 同じ 市区町村 | 住んでいる市区町村の役所 | 転居届を出す | 引っ越し後 2週間以内 | 可 | 不可 |
- 同じ日に役所でできる手続きを済ませておく
→ 新居の役所に書類提出する際に、同時にマイナンバーカードの住所変更をしておきましょう。会社員以外の場合は、国民健康保険や国民年金保険の住所変更も忘れないように。印鑑登録については下記の注意事項で確認してください。 - 免許証の住所変更をする
→ 免許証を持っている人は新居の管轄警察署で免許証の住所変更も忘れずにしておきましょう。
※注1)印鑑登録している人
別の市区町村に引っ越す場合、旧居の役所で「転出届」を出す日と同日に(別日でも問題ないですが面倒なので同日に済ませた方がいいと思います)、「印鑑証明証(印鑑登録カード)の抹消手続き」が必要です。転出届を出しても、この抹消手続きは必要です。また、新居の役所で「印鑑証明証(印鑑登録カード)の登録手続き」が必要です。同じく、転入届を出しても、この登録手続きは必要です。新旧の印鑑登録証の切り替えは忘れがちなので注意してください。
・旧居の役所:
→ 抹消手続き
(「転出届」と同日が効率がいい)
・新居の役所:
→ 登録手続き
(「転入届」と同日が効率がいい)
※同じ市区町村に引っ越す場合は「印鑑登録」の手続きは不要(「転居届」のみでOK)
※注2)代理人による手続き
本人以外の代理人による手続きの場合には別途書類が必要となります。役所によって異なるため、引っ越し前後にお住まいの役所HPで確認してください。
※注3)郵送できるのは「転出届」のみ
郵送による「転出届の手続き」は役所HPにある届出書(郵送届出用など)を印刷して、記入・投函する場合がほとんどです。詳しくはお住まいの役所HPで確認してください。また、「転入届、転居届」は郵送できないので注意してください。「郵送による転出届の提出」は遠くに引っ越した時に役所窓口に行けない場合の特別処置と覚えておけば忘れないと思います。例えば、東京都から沖縄県に引っ越しすると、旧居の東京都にある役所窓口にすぐには行けませんが、新居の沖縄県の最寄りの役所窓口にはすぐに行けるため「転入届」は郵送対応していないというわけです。同じ市区町村内に引っ越す場合に必要な「転居届」も同じ理屈なので、郵送対応していません。
郵送できるのは「転出届」のみ
銀行(保険を含んだ他の金融機関)、会社の住所変更をする
- 銀行の住所変更をする
→ 銀行・生命保険会社などの金融機関に連絡するのを忘れがちになります。
銀行の場合は、新居や勤務先最寄りの支店窓口での手続きになるため、「本人確認書類(顔写真付き)と銀行届出印」を持参して、平日9:00~15:00の時間帯に窓口で手続きしてください。郵送やTELで住所変更の手続きができる銀行もあります。詳しくは自分が使っている金融機関にお問い合わせください。 - 会社に住所変更を報告する
→ 会社への報告はお勤めの総務部(総務を担当する部署)に確認すればわかると思います。
登録している会員サービスの住所変更をする
特に、支払う可能性があるサービスの場合は、忘れずに住所変更しておきましょう。
Amazonなど通販のデフォルト設定住所の変更を忘れて、いつもの癖でワンクリック注文してしまうと旧居に荷物が届いてしまうので注意してください。
<代表的な会員サービス>
・通販「Amazonプライム、楽天、Yahoo!ショッピング、メルカリなど」
・動画配信サービス「YouTube Premium、Netflix、dアニメストアなど」
・漫画アプリ「コミックシーモアなど」
家具、家電、雑貨、食品を購入する
引っ越し初日から1週間のうちに使いそうな物を挙げました。
大型家電
- 照明器具
- 冷蔵庫
- 洗濯機
- 電子レンジ
- 炊飯器
家具
- カーテン
- ベッド(寝具一式)
- テーブル
→ 一人暮らしの場合は「リビングテーブルとダイニングテーブル」は兼用で問題ないと思います。 - ソファ(1人掛けの椅子など)
→ くつろげる場所を確保しておいた方がいいかもしれません。
キッチン用品(自炊を想定する)
- まな板
- 包丁
- フライパン
- 鍋
- ざる・ボウル
- 食器(皿、コップ、箸)、カトラリー(フォーク、スプーン、ナイフ)
→ 生活が落ち着くまでは100均でも買える使い捨て品でいいかもしれません。 - キッチン用洗剤とスポンジ
バス用品(洗面所含む)
- タオル
- ハンドソープ
- 歯ブラシ・歯磨き粉
- ドライヤー
- 化粧品(女性)
- シェーバー(男性)
- ボディソープ
- シャンプーとコンディショナー
- 洗濯用洗剤、柔軟仕上剤
- 掃除用具(バスブラシ、洗剤など)
トイレ用品
- トイレットペーパー
- 掃除用具(トイレブラシ、洗剤など)
健康管理に関するもの
- 救急箱とその中身
→ 「絆創膏、消毒液、体温計」は用意しておいた方がいいと思います。 - 常備薬
洋服
- 1週間分の着替え
→ 引っ越しの片付けなどで時間がなくなり、洗濯できる回数が少なくなる可能性があるため、多めに持っておきましょう。
その他の雑貨
- ティッシュペーパー
- ハンガー(洗濯以外で使用するもの)
- ゴミ箱、ゴミ袋(市区町村指定のゴミ袋の場合あり)
- 洗濯する時に使用する物(洗濯竿、ハンガー、ピンチなど)
→ 洗濯乾燥機なら使用しないかもしれません。
食材や調味料
- 調味料(砂糖、塩、醤油など)
- 食材や飲み物
あれば便利な物
- 工具(ハサミ、カッター、メジャー、ドライバーなど)
- 延長コード
→ 引っ越し後1か月くらいは、突然想定外のことが起こる可能性があります。「1.0m、2.0m、3.0mの延長コード」を各1本ずつ持っていれば安心です。 - 除菌シート
→ お手拭き以外でも使用できるためあれば便利です。
まとめ:HSPが自立するのは大変だが、一歩ずつステップを踏もう
というわけで、「HSPが自立するための事前準備③ ~一人暮らし編~」についてまとめました。
自立することが大切ということはHSPに限ったことではないですが、私がHSPなので、今回はその目線で書いてみました。
- 効率的な引っ越しの手順を知る
- 手続きを段取りよく行う
- ついでに手続きの目的を学ぶ
こうしてまとめると、引っ越しは意外と手間がかかりますね(^^;)
しかし、自立するためにはやはり一人暮らしの経験が必要ですし、必ず自分のためになると思います。このブログ記事が少しでも参考になれれば嬉しいです♪
ここまでブログを読んでくれてありがとうございます。
それでは✿
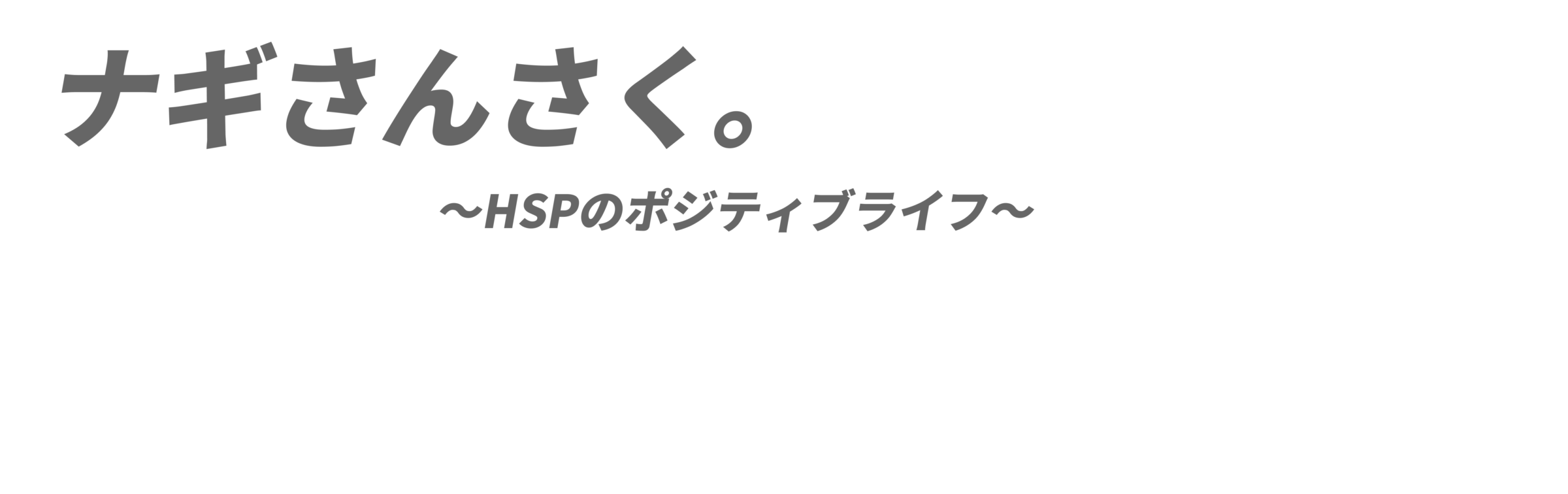





コメント