こんにちは✿
みなさんは、

HSPって病気なの?
という言葉をよく聞きませんか?
私も最初はHSPは病気の類なのかなと思ってましたが、HSPは生まれ持った気質で病気とはまた違うものでした。
そこで、
- 「こういった誤解が生じてしまう理由って何だろう?」
- 「そもそもHSPと精神疾患の違いって何だろう?」
という疑問が浮かんだので、今回のブログ記事では、
- HSPが病気と誤解される理由
- HSPと精神疾患の違い
についてまとめました!
HSPとは?
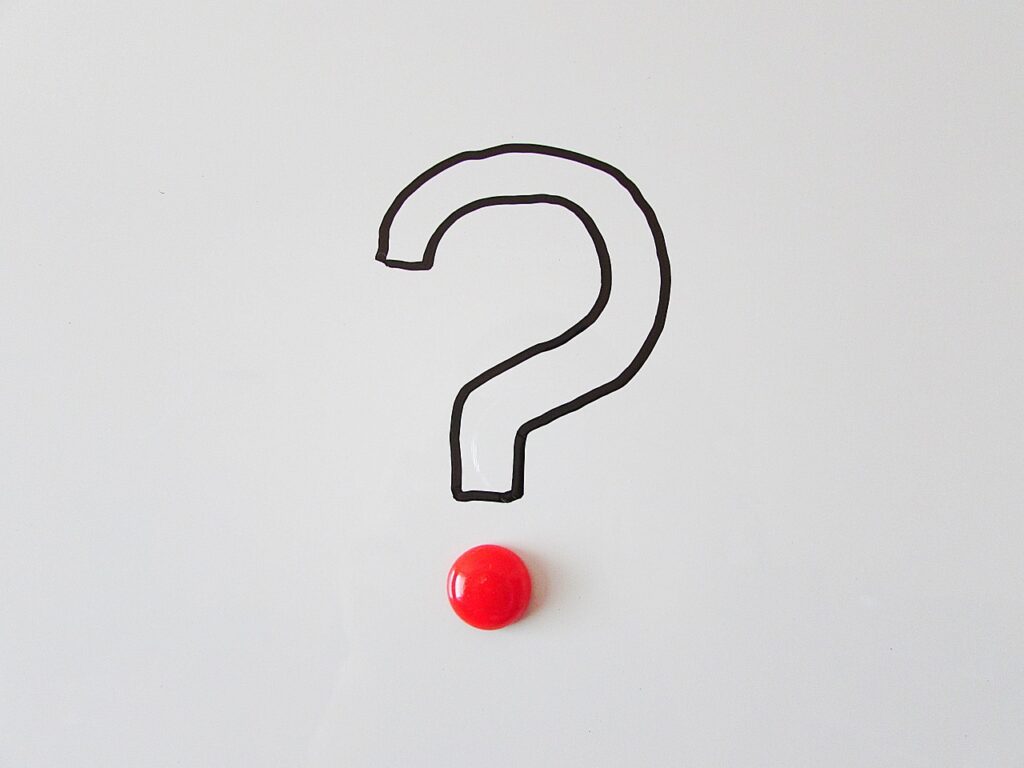
HSPは、Highly Sensitive Person(ハイリー・センシティブ・パーソン)の略称です。なんだか病名のように聞こえるかもしれませんが、これは遺伝子的に生まれ持った気質のことで、アメリカの心理学者であるエレイン・N・アーロン博士が提唱した心理学的概念です。
生まれつき「非常に繊細な人」「敏感な人」「感受性が強い人」などという意味です。
全人口の約5人に1人はこのHSPに当てはまっているそうです。
HSPについてまとめた記事もあるので、興味がある方はぜひ。
HSP関連の本はこちらから。
HSPが病気と誤解される理由

HSPは、その特性から病気と誤解されることが多いです。
その背景には、
- 高い感受性に対する誤解
- 社会的な認識のギャップ
- ストレスとの関係
- メディアや文化の影響
などがあります。
気にしすぎという誤解
HSPは、音や光、匂いなどの刺激に対して非常に敏感に反応します。
また、他人の感情や微細な変化にも敏感に気付きやすいです。この高い感受性は「過敏すぎる」「神経質だ」と見なされることがあります。しかし、これらの感受性は生まれつきの特性であり、本人が意図的にコントロールすることは難しいです。
この誤解は、HSPが自分自身を否定的に捉えてしまう原因にもなってしまいます。
社会的な認識のギャップ
現代社会では、感情を抑え、理性的に振る舞うことが評価される傾向にあります。
そのため、感受性が高く、感情を表に出しやすいHSPは、しばしば「弱い」「頼りない」と見なされることがあります。
この社会的な認識のギャップは、HSPが自分の特性を受け入れることを難しくし、自己肯定感を低下させる要因になってしまいます。
HSPとストレスの関係
HSPは、環境や他人の感情に敏感であるため、ストレスを感じやすい傾向があります。
職場や家庭でのプレッシャー、人間関係のトラブル、過度な騒音や混雑など、日常生活の中でストレスを感じる要因は多岐にわたります。このストレスに対する敏感な反応は、「不安障害」や「ストレス過剰」と誤解されることがありますが、HSPにとっては正常な反応です。
HSPがストレスをうまく管理するためには、適切な環境づくりとまわりからのサポートが必要です。
メディアや文化による影響
メディアや文化の影響も、HSPが誤解される大きな要因です。
多くのメディアでは、感受性の高さが弱点として描かれることが少なくありません。また、文化によっても、HSPに対する認識は異なり、個人の感受性が軽視される傾向にあります。
これらの影響により、HSPは自分の特性を否定的に捉えがちです。
HSPと不安障害の違い

不安障害(Anxiety Disorders)とHSPは混同されがちです。
不安障害の特徴
不安障害は、過剰な不安や心配が続き、日常生活に支障をきたす精神的な障害の総称です。
- 過剰な心配:
日常的な出来事や状況について、実際の危険性に比べて過度に心配することがあります。この心配は、コントロールが難しく、長期間続くことが多いです。 - 身体症状:
動悸、息切れ、発汗、震え、胃の不快感などの身体的な症状が頻繁に現れます。 - 回避行動:
不安を感じる状況を避けるために、特定の場所や活動を避ける行動が見られます。これにより、生活範囲が狭くなり、社会的な孤立を招くことがあります。 - パニック発作:
突然の強い不安や恐怖を感じ、これに伴って激しい身体症状が現れることがあります。この発作は予測が難しく、苦痛を伴います。
不安障害とHSPの根本的な違い
- 刺激に対する反応:
HSPは外部の刺激(音、光、匂いなど)や他人の感情に対して非常に敏感に反応します。これは感受性の高さによるもののため、必ずしも不安や恐怖を伴うものではありません。一方、不安障害の人々は、特定の状況や出来事に対して過度な不安を感じ、それに対して過剰に反応します。 - 不安の持続性と強度:
HSPは特定の刺激に対して一時的に強く反応することがありますが、通常はその状況が過ぎれば感情が安定します。不安障害の場合、不安や心配が続くため、日常生活に支障をきたすことが多いです。 - 生活への影響:
HSPは高い感受性を持つため、ストレスを感じやすい傾向がありますが、適切な環境やまわりからのサポートがあれば、通常の日常生活を問題なく送ることができます。不安障害は、治療なしでは日常生活に重大な影響を及ぼし、仕事や人間関係においても困難を伴うことが多いです。 - 対処法の違い(治療の必要性):
HSPは生まれつきの特性であり、病気ではないため、治療の対象ではありません。一方、不安障害は適切な治療を受けることで症状の改善が期待できます。認知行動療法や薬物療法を通じて、不安の管理や軽減が可能です。
HSPとうつ病の違い

うつ病(Depression)とHSPも混同されることがあります。
うつ病の特徴
- 抑うつ気分:
持続的な悲しみや虚しさ、絶望感を感じることが多く、これがほぼ毎日、少なくとも2週間以上続きます。 - 興味や喜びの喪失:
以前は楽しんでいた活動に対する興味や喜びが著しく減少します。 - エネルギーの低下:
常に疲労感を感じ、些細なことにも疲れやすくなります。日常生活の活動や仕事が困難になります。 - 睡眠の問題:
不眠や過眠などの睡眠障害が見られます。特に早朝に目が覚めてしまうことが多いです。 - 食欲や体重の変化:
食欲が減少し体重が減る、または逆に過食になり体重が増加することがあります。 - 集中力や決断力の低下:
集中力や注意力が低下し、決断を下すことが難しくなります。 - 自殺念慮:
生きる価値を感じられず、死にたいと感じることがある場合もあります。
うつ病とHSPの根本的な違い
- 感受性の高さ:
HSPは外的刺激や他人の感情に対して非常に敏感に反応します。これは、音や光、匂い、温度変化、人間関係などに対する高感受性に由来します。一方、うつ病の症状には、外的刺激に対する感受性の高さは含まれません。 - 感情の持続性:
HSPは感情の起伏が激しいことがありますが、これは一時的なものであり、状況が変われば感情も安定します。うつ病は、持続的な抑うつ気分が特徴であり、一時的な感情の変動とは異なります。 - エネルギーと意欲:
HSPは過度な刺激やストレスにさらされると疲労を感じやすいですが、基本的には日常生活を送る意欲やエネルギーを持っています。うつ病は、エネルギーの低下と無気力が顕著で、日常生活を送るのが難しくなります。 - 対処法の違い(治療の必要性):
HSP適切な環境やまわりからのサポートを得ることで、その感受性を活かして豊かな生活を送ることができます。一方、うつ病は専門的な治療が必要であり、薬物療法やカウンセリングを通じて症状の管理を行います。
HSPと自閉症スペクトラム障害(ASD)の違い

自閉症スペクトラム障害(ASD:Autism Spectrum Disorder)もHSPと混同されることがあります。
ASDの特徴
- 社会的コミュニケーションの困難:
他人との交流やコミュニケーションが難しいことがあります。非言語的なコミュニケーション(ジェスチャー、表情、アイコンタクトなど)や、人間関係を築くことに困難を感じることが多いです。 - 限定された興味と反復行動:
特定の興味や活動に強いこだわりを持ち、同じ行動を繰り返すことがあります。これには、特定のルーティンやパターンに固執することも含まれます。 - 感覚過敏または鈍感:
音、光、匂い、触覚などの感覚に対して過敏であるか、逆に鈍感であることがあります。これは感覚処理によるもので、日常生活に影響を及ぼすことがあります。 - 発達の早期からの症状:
症状は幼少期から現れ、その発達の過程で顕著になります。特に社会的スキルの発達に遅れが見られることが多いです。 - 多様な表現:
スペクトラム(連続体)として捉えられ、その症状の表れ方や程度は個人によって大きく異なります。重度の場合もあれば、軽度で日常生活にあまり影響を及ぼさない場合もあります。
ASDとHSPの根本的な違い
- 感受性の種類と対象:
HSPは外部刺激や他人の感情に対してとても敏感です。これは、音、光、匂い、人間関係などに対する感受性が高いことが要因です。一方、ASDの感覚過敏や鈍感さは、特定の感覚に対する処理の違いによるものであり、必ずしも全体的な感受性の高さを意味するわけではありません。 - 社会的スキルとコミュニケーション:
HSPは他人の感情や微細な変化に敏感に気付くため、対人関係において共感力が高いことが多いです。これに対して、ASDの人々は社会的なコミュニケーションや関係構築に困難を感じることが多く、非言語コミュニケーション(ボディランゲージなど)を読み取るのが難しい場合があります。 - 反復行動と興味の固執:
HSPは興味や活動が多様であることが多いですが、ASDの人々は特定の興味や活動に強く固執し、それに関連する反復行動が見られます。これらの行動はASDの診断基準の一つです。 - 対処法の違い(治療の必要性):
HSPは気質であり、病気や障害ではないため、特別な診断や治療は必要ありません。HSPは自分の特性を理解し、適切な環境やまわりからのサポートを得ることで、日常生活を快適に送ることができます。一方、ASDは発達障害の一種であり、早期の診断と適切な支援が重要です。療育や教育プログラム、行動療法などを通じて、ASDの人々が社会で自立できるよう支援することが求められます。
HSPと注意欠陥・多動性障害(ADHD)の違い

注意欠陥・多動性障害(ADHD:Attention Deficit Hyperactivity Disorder)とHSPも混同されることがあります。
ADHDの特徴
- 注意力の欠如:
集中力がなく、注意力を持続させることが難しく、外部からの指示や課題を無視することがあります。 - 多動性:
不適切な場面で走り回ったり、静かにしていることが難しいとされます。 - 衝動性:
考える前に行動してしまう傾向があります。
ADHDとHSPの根本的な違い
- 注意力の問題:
ADHDの人々は注意力を持続させることが難しく、外部からの指示を無視することがあります。一方、HSPは外的刺激に敏感であるために注意力が散漫になることがありますが、集中力を持続する能力は持っています。 - 多動性と落ち着き:
ADHDは物理的に活動的で、静かにしていることが難しいとされています。一方、HSPは過度な刺激を避けるために静かな環境を好むことが多く、一般的に多動性は見られません。 - 感受性と刺激の処理:
HSPは感覚処理が非常に敏感であり、音、光、匂いなどの外的刺激に対して強い反応を示します。ADHDの人々も感覚過敏を持つことがありますが、その主な問題は注意力散漫や衝動性にあります。 - 行動の衝動性:
ADHDの衝動性は考える前に行動してしまう傾向があります。HSPは慎重で内向的な性格を持つことが多く、衝動的な行動は少ないです。 - 対処法の違い(治療の必要性):
ADHDは神経発達障害であり、専門的な診断と治療が必要です。薬物療法や行動療法を通じて、症状の管理や生活の質の改善に期待できます。一方、HSPは生まれつきの特性であり、治療の対象ではありません。HSPは自分の特性を理解し、ストレスを軽減するための環境づくりやまわりからのサポートを得ることで、健やかに生活することができます。
HSPと境界性パーソナリティ障害(BPD)の違い

境界性パーソナリティ障害(BPD:Borderline Personality Disorder)とHSPも混同されがちです。
BPDの特徴
- 感情の不安定性:
感情が急激に変化し、数時間から数日の間に激しい気分の変動が見られます。これにより、極端な幸福感から深い絶望感に至ることがあります。 - 対人関係の不安定性:
親密な関係において、理想化と価値の低下(devaluation)を繰り返すことが多いです。相手に対する強い愛着や拒絶感を交互に感じることがあります。 - 自己イメージの不安定性:
自己認識や自己イメージが不安定であり、自分の価値やアイデンティティに関して一貫性を欠くことがあります。 - 強い空虚感:
持続的な空虚感や孤独感を感じることが多いです。 - 衝動的行動:
自傷行為や過剰な飲酒、薬物乱用、無謀な運転、暴飲暴食など、衝動的でリスキーな行動を取ることがあります。 - 恐怖と回避:
見捨てられることへの強い恐怖があり、それを避けるために必死になることが多いです。 - 一時的なパラノイア(病的な心配性)や解離症状:
強いストレス下で、現実感喪失やパラノイア的な思考が一時的に現れることがあります。
BPDとHSPの根本的な違い
- 感情の揺れ:
HSPも感情が揺れ動くことがありますが、それは外部刺激やストレスに対する反応であり、BPDのような極端な感情の変動や衝動的な行動は少ないです。HSPの感情の変動は一般的に短期間であり、状況が改善すれば感情も安定します。 - 対人関係:
HSPは他人の感情に対して非常に敏感であり、共感力が高いです。対人関係でのトラブルはあるものの、BPDのように極端な理想化と価値の低下を繰り返すことはありません。HSPは一般的に他人との関係を維持しようと努めます。 - 自己イメージ:
HSPは自己イメージが比較的安定しており、BPDのような自己認識の不安定さや持続的な空虚感は見られません。 - 衝動性:
HSPは内向的で慎重な性格を持つことが多く、BPDのような衝動的でリスキーな行動は少ないです。HSPは感情の処理やストレスへの対処法を学ぶことで、穏やかな生活を送ることができます。 - 対処法の違い(治療の必要性):
HSPは生まれつきの特性であり、治療の対象ではありません。HSPは自分の特性を理解し、適切な環境やまわりからのサポートを得ることで健やかに生活することができます。一方、BPDは専門的な治療が必要であり、長期的な治療計画とサポートが重要です。
まとめ:HSPと精神疾患の症状は根本的に違う
というわけで、「HSPが病気と誤解される理由」と「HSPと精神疾患の違い」についてまとめてみました。
- 高い感受性のせいで神経質だと思われるから
- HSPは弱々しい印象があるから
- HSPはストレスに弱く、病気だと認識されやすいから
- メディアがHSPの感受性を軽視する傾向があるから
- 不安障害
- うつ病
- 自閉症スペクトラム障害
- 注意欠陥・多動性障害
- 境界性パーソナリティ障害
これは私が個人的に気になって調べたもので、どうせならと思いブログ記事にしました。
こうして見ると「HSPは病気」って誤解されやすそうだなと思いました。というか誤解されても仕方ないなと思います。HSPの特徴は少し「かよわい」というイメージを持たれるので(^^;)
しかし、大切なのはHSPは病気なのか、HSPは誤解されやすいのはなぜかという論争よりも「HSPという特性にどう自分が向き合うか」だと思います。
HSPや精神疾患の知識を持っておくのも大事ですが、その肩書きにばかりとらわれないのも重要かなと思います。
ここまでブログを読んでくれてありがとうございます。
それでは✿
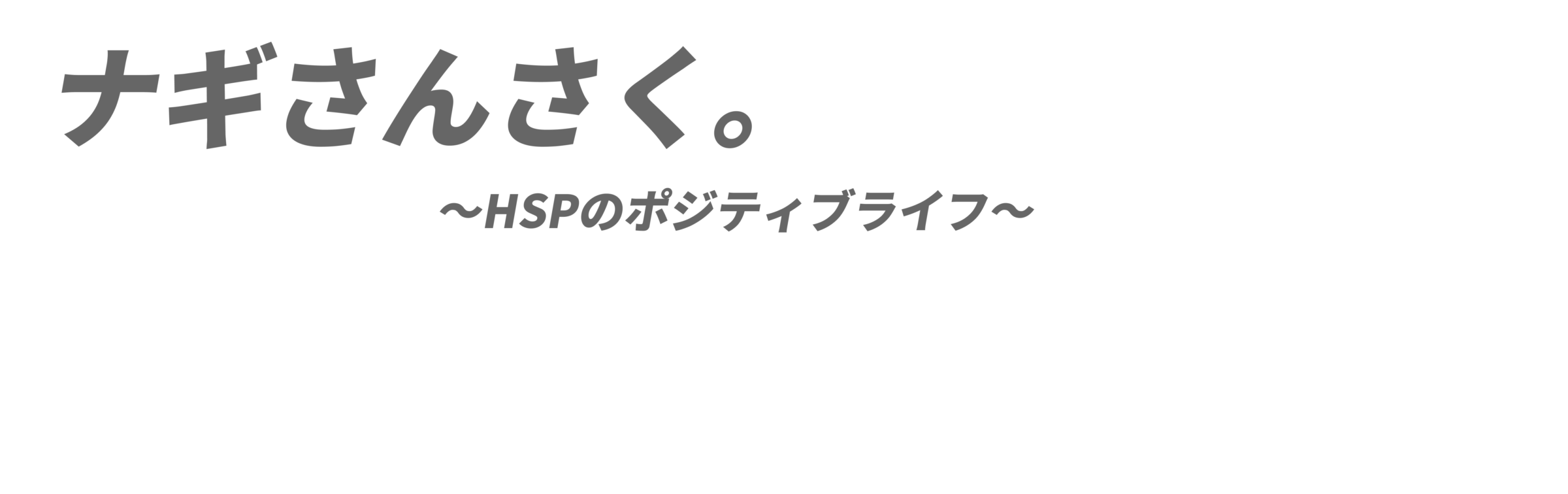



コメント